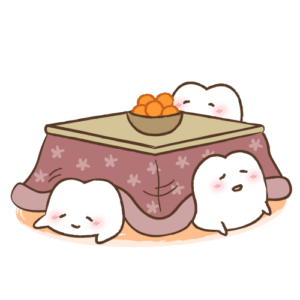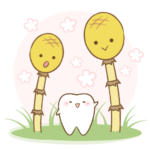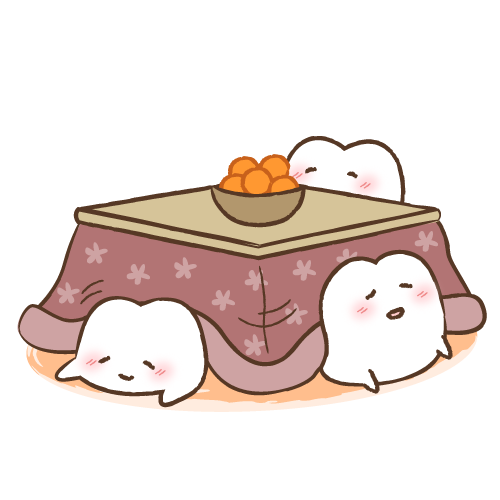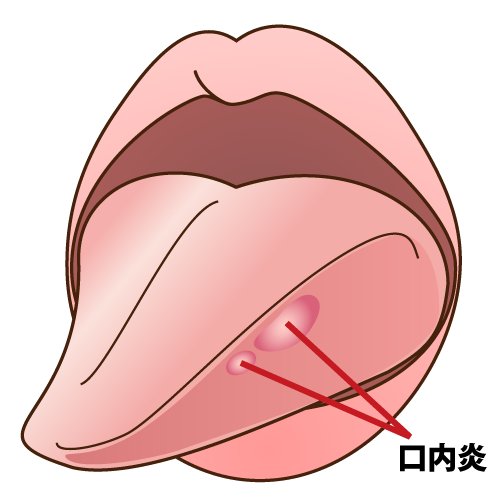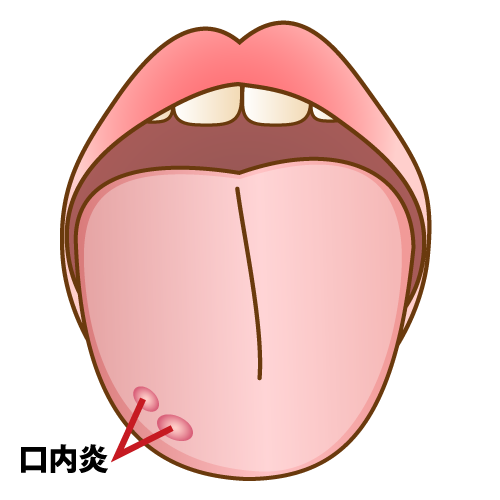⸻
唾液は、体と心を映す鏡です
唾液は、
虫歯や歯周病を防ぎ、細菌やウイルスの侵入を抑え、
さらに全身の健康や美容にも深く関わっています。
最近では、
**「唾液の量」だけでなく「唾液の質」**
その質を左右する大切な要素が、**IgA(免疫グロブリンA)
**IGF(インスリン様成長因子)**です。
⸻
唾液の質を守るIgA抗体とは?
IgAは、口や喉、腸などの粘膜を守る免疫物質です。
唾液中にしっかり含まれていることで、
・虫歯や歯周病の予防
・口内炎ができにくい
・感染症にかかりにくい
といった効果が期待できます。
つまり、**IgAは「体の入り口を守る免疫の盾」**
⸻
IgAは「腸」で作られている
IgAの多くは、実は腸管で作られています。
そのため、腸内環境を整えることが、
おすすめなのが発酵食品。
・ヨーグルト
・納豆
・キムチ
これらに含まれる善玉菌は腸内環境を整え、腸管免疫を活性化し、
IgAの分泌をサポートします。
「よく噛んで、腸にやさしい食事をすること」
それだけで、唾液の質は少しずつ変わっていきます。
⸻
唾液と美肌をつなぐIGFの存在
唾液には、微量ながら**IGF(インスリン様成長因子)**
IGFは、
・細胞の修復
・新陳代謝のサポート
・ターンオーバーの維持
といった働きを持つ成長因子です。
唾液中のIGFが直接肌に作用するわけではありませんが、
体の回復力や再生力を支える環境を整えることで、
結果的に肌の調子が整いやすくなると考えられています。
⸻
ビタミンCは唾液にもやさしい栄養素
ビタミンCは、唾液を直接増やす成分ではありません。
しかし、
・抗酸化作用
・免疫細胞のサポート
・ストレス軽減
を通して、自律神経を整え、
また、IgAの働きを支える栄養素でもあり、
口内炎や歯ぐきのトラブル予防にも役立ちます。
※酸性飲料の摂りすぎには注意し、
⸻
唾液を増やすのは「がんばらない習慣」
唾液の分泌は、自律神経と深く関係しています。
おすすめなのは、
・楽しく歌を歌う
・ヨガやストレッチ
・ゆっくりした散歩
こうしたリラックスできる運動です。
副交感神経が優位になり、IgAの分泌も促されます。
一方で、過度な筋トレや激しい運動は、
一時的にIgAを減少させることがあります。
⸻
顎下腺マッサージで、唾液力アップ
顎の下にある顎下腺は、
やさしくマッサージすることで唾液分泌が促され、
IgAの刺激にもつながります。
毎日のちょっとしたケアが、口と体を守ります。
⸻
まとめ 〜「暇」が唾液と美肌を育てる〜
私は今『退屈と暇の倫理学』の本では、
「何もしない時間」「役に立たない時間」
実は唾液も同じです。
忙しすぎる毎日、
効率や成果ばかりを求める生活では、
唾液は減り、免疫も、美しさも損なわれていきます。
ゆっくり噛む時間、ぼんやり散歩する時間、
何もしない“暇”な時間こそが、
唾液を育て、体を修復し、肌を整える。
唾液は、
「がんばらない生き方」を教えてくれる、
体からのやさしいメッセージなのかもしれません。


 絶滅の理由は
絶滅の理由は